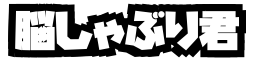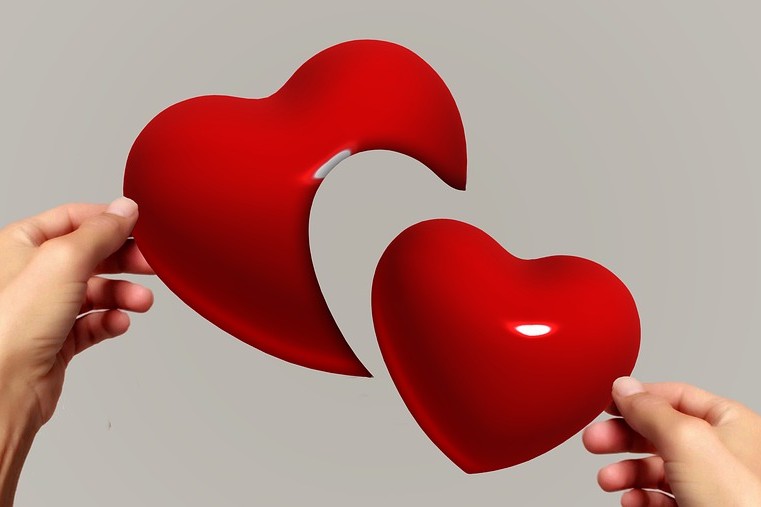「感情」の定義は非常に曖昧です。
「感情」という用語自体は日常的によく使いますし、学術的な用語としての「感情」との線引きが難しいです。さらに、「情動」という用語との違いも不明瞭と言えます。
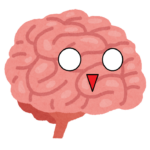
どうしてそんなことになっちゃったんだろう…
今回は、そのことも含め、解説していきます。
「感情」の定義づけは難しい
そもそも、感情とは何かという問いに対し、ズバリこれでしょう!と答えることは難しいです。
理由としては、以下の問題点が挙げられます。
- 「感情」は、学術用語でもあるが、日常語でもあり、多義的で曖昧。
- 他言語との対応関係が難しい。
他言語との対応関係は難しいですが、欧米等諸外国の先行研究を無視することもできません。
他言語、特に、英語における「感情(emotion,affect,feeling)」を念頭におきつつ、感情の定義を考える必要があります。
英単語との対応
- affect=感情
- feeling=感情
- emotion=情動、感情
emotionのみ、「情動」という訳され方をします。
これには、哲学者・啓蒙思想家である西周が、emotionを情緒と初めて訳し、それが次第に「情動」へと変遷していったという経緯があります。
「emotion=情動」という翻訳は、日本の心理学者には馴染んでいますが、一般に向けて説明をする際などには、感情と訳したほうが良い場合もあり、「emotion=情動」が絶対だと言い切ることは難しいと思われます。
emotion,affect,feelingそれぞれの意味の詳細
affect
広義の感情。
- emotion
- feeling
- mood(気分)
- sentiment(感情傾向)
- emotional attitude(感情的態度)
を含む包括的概念。
feeling
主観的な気持ち。
「良い感じ」などの漠然とした快・不快や、「悲しい気持ち」などの個別感情など、主観的側面にスポットした用語。
「なんとなく落ち着かない」、「ワクワクする」といったものもfeelingの一例です。
emotion
個別の感情。
喜怒哀楽など、特定の出来事に起因する個別の感情。
ただ、定義は未統一であり、未だ議論は続いています。
まとめ
以上のことから、感情と情動の違いを語る際には、英単語に触れる必要があることがわかるでしょう。
情動に関しては、喜怒哀楽といった個別の感情のことだと言うことができるかと思います。
しかし、その定義も確定的と断言することはできません。
考え続ける必要のあるトピックですね。