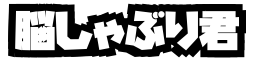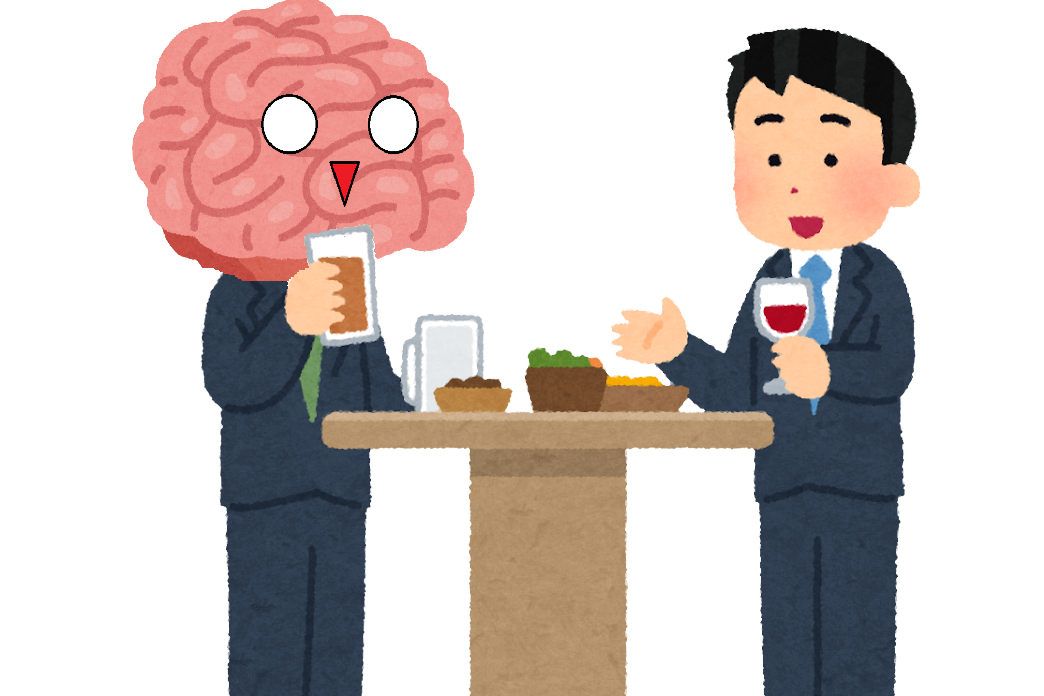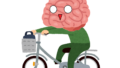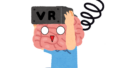デメリットにばかりスポットが当てられがちですが、アルコールを摂取することにはメリットも存在します。
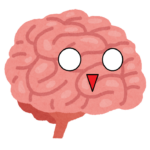
え?当たり前じゃん。メリットがあるからこそお酒はこんなに世界中で愛されてるんでしょ。
その通りです。
肝臓などには負担をかけるアルコールですが、そういったデメリットに目をつぶれば、一時的にバフのようなものを得られるのです。
今回は飲酒のメリットも含め、アルコールについて詳しくなりましょう!
アルコールの基礎知識
アルコールについて
主成分はエタノール(エチルアルコール)。
飲まれたアルコールは、消化管を通り、小腸から吸収され(胃からも少し吸収される)、門脈(消化器官から肝臓へと繋がる血管)を通り、肝臓で主として代謝されます。
摂取されたアルコールの約90%はそのように代謝されますが、残りのアルコールは、尿などに含まれて排出されたり、肺から排出されたり、あるいは、その他の臓器で代謝されたりします。
脳への作用
アルコールを摂取すると、脳では…
①大脳皮質(理性を司る部位)の機能が抑制される。
②通常、大脳皮質によって抑制されている大脳辺縁系・視床下部の活動が活発化する。→感情が表れやすくなる。
③さらに過剰摂取をすると、脳幹(呼吸などを制御している部位)が麻痺する。→生命の危険に陥る。
また、アルコールは、摂取すればするほど脳が委縮します。
酔いの目安
体重60kgの成人の場合、血中エタノール濃度(%)が、
- 0.02~0.04%(ビール瓶1本程度)=爽快期
- 0.05~0.10%(2本程度)=ほろ酔い初期
- 0.11~0.15%(3本程度)=ほろ酔い極期
- 0.16~0.30%(5本程度)=酩酊期
- 0.31~0.40%(7~10本程度)=泥酔期(意識が不明瞭)
- 0.40~0.50%(10本以上)=呼吸困難となり、最悪死亡
※個人差はあります。
飲酒のメリット
社会的ストレスの低減
アルコールを摂取すると、人の表情に対してマイナスな感情を抱きづらくなります(M.A.Sayette et al., 1992)。
相手が怪訝な表情をしていた場合、通常、それは自分への敵意と捉えられます。自分が敵意を向けられているということは不快、あるいは不安なことであり、ストレスの原因となります。
しかし、アルコールを摂取すると、通常なら不安を引き起こすような情報に対してポジティブな評価を行うようになります。その結果、ストレスが軽減されることになるのです。
気前が良くなる
アルコールの摂取量が増えると、それに従って支払うチップ額も増加したという研究結果があります(M.Lynn, 1988)。
気前が良い人は周りからの印象も良いです。人から好かれやすくなる効果も期待できるかもしれません。
つまり、気分が良くなるってこと
アルコールを摂取すると、通常ならストレスを感じるような状況でもネガティブな感情を抱きにくくなり、気分が楽になるということです。また、気前が良くなり、周囲の人への接し方がより寛大になる傾向もあります。その結果、人間関係が円滑になりやすく、社交的な場面で良い印象を与える可能性が高まると考えられます。
しかし、これらのメリットは、あくまでも適量の飲酒によるものです。過度な飲酒では、認知機能の低下のほうが目立ってしまうため、むしろ人間関係に亀裂が入ってしまう可能性すらあります。
健康や品性を保つためにも、節度をもった飲酒を心がけましょう。
参考文献
- M.A.Sayette, D.W.Smith, M.J.Breiner, G.T.Wilson(1992). The effect of alcohol on emotional response to a social stressor. Journal of Studies on Alcohol, 53(6), 541-545.
- M.Lynn(1988). The Effect of Alcohol Consumption on Restaurant Tipping