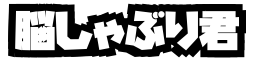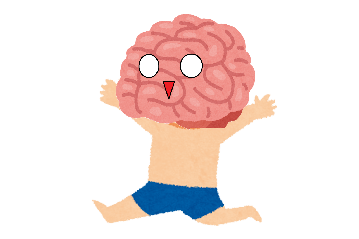ADHDとは?
ADHDは、Attention-Deficit/Hyperactivity Disorderの略。日本語に訳すと、「注意欠如・多動性障害」といったところでしょうか。多動のないものはADDと呼ばれます。
ADHDは、以下の3つの基本的な症状をもちます。
- 不注意
- 衝動性
- 多動性
これらの症状が、発達段階にふさわしくない形で持続的に現れる疾患です。日常生活や学習、仕事、人間関係などに大きな支障をきたすことがあります。
DSM-Vによると、有病率は、小児期5%、成人期2.5%です。
ADHDの基本的な症状
詳細な診断基準は、記事の最後で紹介しますが、大まかな特徴は以下の通りです。
不注意
- 集中力が続かない
- 忘れっぽい
- 課題を順序立てて進めるのが苦手
- 物をよくなくす
衝動性
- 順番を待つのが難しい
- 人の話を遮って話し出す
- 考える前に行動してしまう
多動性
- じっとしていられず、手足を動かす
- 静かな活動が苦手
- おしゃべりが多い
- 動き回るような落ち着きのなさ
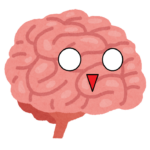
☆捕捉ポイント
- 子どもに多く見られるが、大人になっても続くことがある。
- 症状は、家庭、学校、職場など複数の場面で現れる。
- 多くの場合、学業成績や対人関係、仕事に影響が出る。
ADHDの原因
ADHDの原因には、以下のような要素が関わっていると考えられています。
- 遺伝的要因
- 脳の構造や機能の違い(実行機能や報酬系が十分に機能しない)
- 神経伝達物質の働きの違い
ADHD症状の背後にある脳の仕組み
脳の「報酬システム」の働き方が違う
私たちの脳は、「いいことが起こる予感(報酬の予測)」があると、ドーパミンという神経伝達物質が分泌されます。例えば、「この宿題を終えたらゲームができる」と思ったとき、脳は宿題をする前から”やる気ホルモン”を出すのです。健常な脳では、報酬(ご褒美)が繰り返されると、このようにドーパミンの分泌はだんだん”予兆”に反応するようになります。
▼しかし、ADHDの人は…
この「ドーパミンの予測的な分泌」がうまく起こらないことが示されています。
- 「将来のために今頑張る」が難しい
- すぐに報酬(ご褒美)がないとやる気が出ない
- すぐに報酬がないとやり続けることができない
つまり、
- 遠い目標には取り組めない(不注意)
- 待てない(衝動性)
- 我慢できない(多動性)
ADHDの子どもへの適切な接し方
①すぐに褒めてあげる
- ADHDの子は「後で褒める」よりも、すぐに反応してもらえるほうが行動が定着しやすい。
- 良い行動を見たら、すぐに言葉や視線、ジェスチャーで褒めてあげましょう。
②小さなことでご褒美をあげる
- 長いタスクをいきなり出すと集中が続かないので、小さいゴールに分けてあげましょう。例えば、「1ページやったらスタンプ」「5分間だけ座っていられたらポイントをあげる」など。
- 長時間の待機や我慢は苦手なので、ゲーム感覚で少しずつ慣れていくことが大切。
③ご褒美を”見える化”してあげる
- スタンプカード、タイマーなど、目に見える形で進捗や報酬を表すことで、やる気を出させてあげます。ドーパミンの予測的分泌を促すには視覚的サインが有効です。
④行動と本人を分けて叱る
- ADHDの子は「怒られてばかり」という自己イメージを持ちがちです。
- 行動を正すときは、「あなたがダメ」ではなく、「この行動はダメだよ」と具体的に冷静に伝えましょう。自己肯定感が育つと、長期的な行動変化に繋がりやすいです。
ADHDの診断基準(DSM-V)
DSM-Vでの診断基準は以下の通りです。
A. 機能または発達を妨げる不注意および/または多動・衝動性の持続的なパターン
1.不注意
以下の症状のうちで6つ(17歳以上では5つ以上)が、少なくとも6カ月以上持続し、発達水準にそぐわない程度で、社会的または学業・職業活動に直接的な悪影響を及ぼしていること。
a. 細部に注意を払えず、学業・仕事・他の活動で不注意なミスをする。
b. 課題や遊びの活動で注意を持続することが困難。
c. 直接話しかけられても聞いていないように見える。
d. 指示に従わず、課題や業務をやり遂げられない。
e. 課題や活動の整理が苦手。
f. 精神的努力を要する課題を避けたり嫌がったりする。
g. 課題に必要なものをよく失くす。
h. 外部の刺激に注意を逸らされやすい。
i. 日常的な活動を忘れやすい。
2.多動性・衝動性
以下の症状のうち6つ(17歳以上では5つ以上)が、少なくとも6カ月以上持続し、発達水準にそぐわない程度で、社会的または学業・職業活動に直接的な悪影響を及ぼしていること。
a. 手足をそわそわ動かす、または座っているときに身体をねじる。
b. 座っているべき場面で席を離れる。
c. 不適切な場面で走り回ったりよじ登ったりする。
d. 静かに遊んだり余暇活動をすることができない。
e. 常に動いているように見える。
f. おしゃべりが過ぎる。
g. 質問が終わる前に答えを言う。
h. 順番を待つのが苦手。
i. 他人の会話やゲームに割り込む。
B. 一部の不注意または多動・衝動性の症状が12歳以前に存在していた。
C. 症状が複数の状況(例:家庭、学校、職場など)で認められる。
D. 社会的、学業的、職業的機能を妨げている明確な証拠がある。
E. 他の精神障害(統合失調症、気分障害など)のみで説明されない。